「マッチングイベントを企画してみたいが、何から手を付けるべきかわからない」
「過去に実施したが、期待したほど成果が出なかった」
――こうした声は、法人・行政・業界団体など主催側の現場から多く聞かれる課題です。
マッチングイベントは、異業種連携・学生採用・自治体の地域活性・スタートアップ支援など、さまざまな分野で活用が広がっている一方、企画・設計を誤れば「ただ集めて終わるだけ」の場になりがちです。
そこで本記事では、以下のような法人担当者の課題を解決すべく、
- そもそもマッチングイベントとは何か?その目的と仕組み
- 成果につながるイベントの種類と設計の違い
- 事前準備から当日進行・フォローアップまでの具体的フロー
- よくある失敗と成功企業の運営ポイント
- オンライン対応やツール選定のヒント
- 運営担当が押さえるべきチェックリスト
などを実務に直結するレベルで網羅的に解説していきます。
成果を生むマッチングイベントは、「つなげる」前に「設計する力」が成否を分けます。
このガイドが、御社のイベント企画・実施を成功へ導く一助となれば幸いです。
マッチングイベントとは?基本概要と注目される理由

マッチングイベントは、単なる交流の場ではなく、参加者同士の「具体的な成果」や「ビジネス機会の創出」を目的とした出会いの場です。
近年では採用活動、業務提携、スタートアップ支援、地域活性化など、多様なシーンで導入されており、単なる名刺交換にとどまらない“課題解決型の場”として注目を集めています。
この章では、主催・運営側の立場から、マッチングイベントの基本をしっかり押さえるために、以下の3つのポイントを解説します。
- イベントとしての構造と特徴
- 現在注目されている背景
- 活用されている代表的な分野
マッチングイベントの定義と仕組み
マッチングイベントとは、特定のテーマや目的に基づいて、参加者同士の出会いと交流を促し、具体的な成果(採用・連携・契約など)に結びつけることを目的とした交流型のイベントです。
単なる展示会やセミナーと違い、「情報発信」よりも「相互対話」「つながり」「実行への一歩」が主眼に置かれる点が大きな特徴です。
この仕組みでは、主催者は参加者の属性や目的を事前に把握し、最適な組み合わせや対話のきっかけを設計する役割を担います。たとえば、以下のようなフローで進行します。
まず、参加者はイベント申込時に自身のプロフィールや希望条件(求めている相手像、目的、課題など)を入力します。
主催者はこの情報をもとに、事前にマッチングの候補を抽出したり、参加者に応じたセッションや1on1面談の組み合わせを決定します。
イベント当日は、個別面談やテーマ別交流、プレゼンタイム、ワークショップなどを通じて、自然な形での出会いや対話を促進します。
イベント終了後には、アンケートやマッチング希望の再申請、個別フォローの仕組みなどを設けることで、一過性ではない“継続的な関係”へと発展させる仕組みが整えられているのが理想です。
このようなプロセスがなぜ重要かというと、現代のビジネスや採用シーンにおいては、「効率よく出会える」だけではなく、「信頼や相性を見極められる場」が求められているからです。
メールやSNS、オンライン広告では決して補えない、“リアルな相互理解”を短時間で実現できる仕組みとして、マッチングイベントの価値は急速に高まっています。
たとえば、ある中小企業向けのビジネスマッチング会では、「●●業界の営業戦略に悩んでいる」と登録した企業に対し、異業種ながら同じ課題を経験し乗り越えた企業をマッチング相手として提案。
面談後にはノウハウ共有だけでなく、新たな販路連携という具体的な成果につながった事例もあります。
このように、マッチングイベントは「ただ出会う」だけでなく、課題に対する具体的なアクションの起点となる設計こそが、最大の価値であり、企業や自治体が活用すべき理由でもあるのです。
なぜ今、マッチングイベントが注目されているのか
マッチングイベントが今、さまざまな業界や地域で再評価され、導入が加速している背景には、社会構造・ビジネス環境の急激な変化があります。
単なる出会いの場ではなく、「成果の出せる交流施策」として注目されているのです。
まず1つ目の大きな要因は、人材不足の深刻化と採用競争の激化です。
とくに地方企業や中小企業においては、求人媒体や採用広告では十分な母集団形成が難しく、採用コストだけが膨らんでしまう傾向にあります。
こうした中、マッチングイベントを活用すれば、企業が「待つ」姿勢から「出会いを創る」主体的な採用戦略に切り替えることができるため、注目が集まっています。
たとえば、ある地方自治体が主催した「U・Iターンマッチングフェア」では、東京在住の地方出身者を対象にした出会いの場を設計。
参加企業がリアルに話すことで、「求人票では伝わらなかった安心感が持てた」と評価され、イベント後の移住決断率が通常の広報施策と比べて2倍以上に上昇したという結果も報告されています。
次に、業界・企業を超えた連携やオープンイノベーションへのニーズもマッチングイベントを後押ししています。
デジタル化やグローバル化、そして持続可能な社会への移行など、企業を取り巻く課題は複雑化しており、「自社だけで解決できる課題はほとんどない」とも言われます。
このような背景のもと、異業種・異分野とつながる“共創の場”として、ビジネスマッチング型イベントが積極的に開催されるようになりました。
実際に、ある製造業支援機関が開催した異業種マッチング会では、建設機械メーカーと農業用機器メーカーの技術者同士がつながり、意外な共通課題である「屋外環境下での操作性・視認性」に関するノウハウを共有。
その後、共同開発の動きに発展した例もあります。
このように、短時間で共通点を発見し、連携を検討できる環境としての機能性が注目されています。
さらに、リアルとオンラインの融合によって参加のハードルが下がったことも大きな要因です。
かつては遠方からの参加や物理的な会場制約がネックとなり、参加率の向上に苦労していた主催者も多く存在しました。
しかし今では、Zoomや特化型マッチングツールの普及により、地理的距離を超えて人と人をつなぐイベントが柔軟に設計できるようになっています。
これにより、たとえば「首都圏のスタートアップと地方自治体の課題解決」「国内外の投資家とのピッチマッチング」など、従来では成立しにくかった組み合わせが、実際に成果を生む場として機能するようになりました。
最後に見逃せないのが、時代の空気感の変化です。
参加者側の意識も「大量の情報を一方的に受け取る場」から、「リアルな会話の中で共感・納得できる場」へと移り変わっています。
そのため、「話せる」「感じ取れる」「質問できる」マッチングイベントのような双方向型の場が選ばれるようになっているのです。
つまり、マッチングイベントは単なるトレンドではなく、“企業が人と出会い、つながり、動き出すための新しいインフラ”としての立ち位置を確立しつつあると言えるでしょう。
マッチングイベントが活用される主な分野
マッチングイベントは、単なる名刺交換や交流の枠を超え、目的に応じて成果に直結する“戦略的な出会いの場”として、幅広い分野で活用されています。
特に近年では、「人材不足の解消」「地域課題の連携解決」「事業創出・投資促進」など、業界横断的なニーズに応える柔軟な設計が可能なため、行政・民間を問わず導入が進んでいます。
以下に代表的な分野と具体的な活用ケースを紹介します。
■ 採用・就職支援系
新卒採用や中途採用、地域での人材確保など、採用戦略の一環として活用されています。
企業側にとっては自社の魅力をダイレクトに伝えられる場であり、学生や求職者にとっては「人」を通じて企業の雰囲気を体感できる貴重な機会です。
- 【事例】Uターン希望者向けの地方自治体主催「ふるさと就職マッチングフェア」
→ 地元企業×都市部学生が1on1で面談し、内定・移住に直結した成功例あり - 【事例】理系特化型マッチングイベントで、企業が若手研究者と直接対話し採用へ
■ ビジネスマッチング(異業種連携・営業促進)
中小企業・スタートアップ・大企業などが連携や取引先を見つける手段として有効です。
新技術の活用、外注先開拓、販路拡大など、さまざまなニーズに応じて企画されます。
- 【事例】中小企業基盤整備機構が主催する「異業種連携マッチング会」
→ ITベンチャー×製造業の技術提携に発展 - 【事例】VC・投資家とスタートアップをつなぐ「資金調達ピッチマッチングイベント」
→ 1社10分のピッチ&面談形式で、複数社が後日資金調達に成功
■ 地域創生・移住支援・行政連携型
地域課題の解決、UIJターン促進、地元企業の活性化など、行政主導のマッチングイベントも増加しています。
民間企業と地域資源(人材・土地・事業)をつなぐきっかけづくりとして高い効果を発揮します。
- 【事例】長野県主催「信州ワーク&ライフマッチングフェア」
→ 地元企業×移住検討者が交流し、就職・起業・農業参入など多様な成果を創出 - 【事例】空き家所有者×移住希望者×建築業者の三者マッチングイベント
→ 空き家の活用+住民流入という地域再生の一手に
■ 技術・業界特化型マッチング
特定の業界や課題に焦点を当てたマッチングイベントは、参加者の関心度が高く、商談率や連携確度も高い傾向にあります。
専門性の高い人材や企業が集まりやすいため、深い情報交換や長期的連携に発展しやすいのが特長です。
- 【事例】医療・介護業界限定の人材・技術マッチングイベント
→ 看護師・介護士と採用企業、福祉機器ベンダーと医療法人が出会う - 【事例】エネルギー分野の「脱炭素×地方企業」技術連携会
→ 大手企業の技術シーズと中小企業の実装力が結びつき、官民連携プロジェクトへ発展
■ 教育・産学連携・インキュベーション
大学や研究機関と企業、またはスタートアップ支援機関との連携を促すイベントも急増しています。
アイデア段階から事業化・社会実装に向けたマッチング設計が注目されています。
- 【事例】産学官共創プラットフォームによる「学生×企業×地域」アイデアソンマッチング
- 【事例】大学発ベンチャーと民間企業をつなぐ研究成果実装マッチングイベント
▼分野に応じて“出会いの質”をデザインできるのが最大の強み
マッチングイベントは、採用・営業・地域振興・共創・研究開発など、さまざまなシーンで汎用的に活用できるのが最大の特長です。
- 業界・目的・参加層に応じてイベント形式を柔軟にカスタマイズ可能
- 1on1/テーマ別交流/ピッチ形式など多様な構成で目的達成を支援
- “出会いの場”というより、“成果の場”として設計する発想が重要
自社や自治体の課題に照らし合わせて、どの分野で、どのような出会いを創出するべきかを明確にすることが、イベント設計の第一歩となります。
マッチングイベントは“成果志向の場づくり”がすべて
マッチングイベントは、従来の交流会や説明会とは異なり、明確な目的・ターゲット・仕組みを持ってこそ成果を発揮するイベント形式です。
- 単なる接点作りではなく、「何を得て、何を生むか」を設計する
- 社会的課題やビジネス課題の“解決起点”として再評価されている
- 多様な分野で成果を出せるスキームとして拡大中
次章では、それぞれの分野で使われるマッチングイベントの種類と特徴をさらに深掘りしていきます。
ターゲットや開催目的に応じて、最適な形式を選べるようになるためのヒントをお届けします。
マッチングイベントの主な種類とそれぞれの特徴

マッチングイベントと一口に言っても、目的や対象によって形式も内容も大きく異なります。
そのため、「何をつなげたいのか」「どんな成果を目指すのか」を明確にしたうえで、イベントのタイプを最適に選ぶことが成功の第一歩です。
この章では、マッチングイベントの主な4種類を紹介し、それぞれの特長・活用例・企画のポイントを解説します。
ビジネスマッチングイベント(異業種交流・連携促進)
異業種間の提携・取引・共創を目的とした法人向けイベントです。
展示会や商談会と異なり、特定のテーマや課題に沿って、パートナー候補同士のマッチング精度を高める設計がされています。
「特徴」
- 課題・ニーズを事前ヒアリングし、マッチング精度を高めた1対1商談形式が多い
- 中小企業×大手企業、ベンチャー×金融機関など、規模・立場を超えた連携も可能
- 展示会の併催や、プレゼン・ピッチ形式との組み合わせも効果的
「活用例」
- 製造業向け技術連携マッチング会
- 商工会議所主催の異業種連携イベント
- 民間主催のビジネス交流・共同開発促進イベント
異業種間の提携、取引、そして共創を目的とした、法人向けの戦略的なイベントです。
一般的な展示会や商談会とは異なり、参加企業の課題やニーズを事前にヒアリングすることで、互いに最適なパートナーを見つけ出すためのマッチング精度を最大限に高めています。
中小企業から大手企業、ベンチャー企業と金融機関といった、規模や立場を超えた連携も積極的に支援しており、これまでにない新たなビジネスモデルやイノベーションの創出に貢献します。
展示会との併催や、プレゼンテーション形式との組み合わせによって、より効果的な交流を促進することも可能です。
製造業の技術連携から、商工会議所主催の地域活性化イベント、そして民間主導の共同開発促進まで、多岐にわたる分野で活用されています。
このイベントは、具体的な課題解決や、新しいビジネスチャンスの創出を目指す企業にとって、最適なプラットフォームとなるでしょう。
就活・採用マッチングイベント(学生・企業向け)
新卒採用・若手採用の手法が多様化する中で、就活・採用マッチングイベントは企業と学生を“対等な立場”でつなぐ場として注目を集めています。
従来の合同説明会や求人媒体では見えにくかった“人柄・相性・共感”といった要素が、直接対話を通じて把握できるのが最大の特長です。
なぜ今、採用マッチングイベントが必要なのか?
- 求人票や企業サイトだけでは伝わらない社風・職場の雰囲気を感じてもらえる
- 学生の志向も「安定志向」から「人・価値観重視」へと変化しており、対話の場を重視する傾向が強まっている
- Z世代は、オンライン上でのやり取りに慣れている一方、リアルや双方向の接点を通じて“選ばれる企業かどうか”を判断する
このような背景から、単なる会社説明や求人紹介ではなく、“相互理解”を重視したマッチング型イベントへのニーズが高まっているのです。
「主な形式と設計ポイント」
就活マッチングイベントは、以下のような形式が効果的です。
ターゲットやイベント目的に応じて、交流形式を工夫することでマッチング率と満足度が向上します。
- 1on1トークセッション(時間固定)
企業と学生が1対1で5〜15分ずつ対話。希望条件に基づく事前マッチングあり。 - 逆求人型プレゼン(学生が自己PR)
学生が“自分を売り込む”スタイルでプレゼンし、興味を持った企業が声をかける。 - グループ座談会形式
テーマ別に学生・若手社員が少人数でトーク。「会社説明会」よりもラフで深い話がしやすい。 - ピッチ&スカウト型(企業が3分プレゼン)
短時間で企業の魅力を伝え、気になった学生がその場で応募・面談を希望。
「成功事例」
- 地方自治体×地元企業 × 大学キャリアセンター連携の「地域就職マッチングフェア」
→ 参加企業は20社程度に絞り、各社と学生が30分ずつ対話。イベント後の内定率が例年比で1.5倍に。 - IT企業による理系学生特化型マッチング会(オンライン開催)
→ エンジニア志望学生と現場社員の1on1形式で実施。「開発環境が具体的に聞けた」という声が多く、内定承諾率が向上。
企業側にとっての導入メリット
- 短期間で複数の学生と濃い対話ができる(歩留まりの高い採用に直結)
- 会社の“空気感”を伝えられ、ミスマッチを防げる
- 現場社員・若手社員を巻き込むことで、ブランディング効果が高まる
- 他社との比較の中でも、自社の強みを印象付けやすい
また、企業が“選ぶ側”から“選ばれる側”への転換が求められる今、こうした対話型イベントは、学生との信頼構築をスタート地点からつくれる重要なチャネルとなります。
学生側の参加メリット
- 直接質問できることで不安が解消されやすい(待遇・人間関係・やりがいなど)
- パンフレットや企業HPでは分からない“人”の印象で企業を判断できる
- 気軽に参加できる形式が多く、“就活の練習”にもなりやすい
特に「どんな企業を見たらいいか分からない」と悩む就活初期の学生には、マッチングイベントをきっかけに視野を広げられるという効果もあります。
▼対話こそが採用の質を高める
就活・採用マッチングイベントは、単なる採用手段ではなく、“企業のあり方そのもの”を伝えるブランディングの場として機能します。
- 学生にとっては「相性のよい会社」との出会いの機会
- 企業にとっては「理解の深い応募者」とつながるチャンス
- 双方にとって、“納得して進める採用”の入口になる
今後の採用活動において、いかに“人と人が向き合える場”を用意できるかが、企業の採用力を左右する時代になっています。
地域創生・行政系マッチングイベント
自治体・地域団体が主催する、移住・定住促進や地域活性を目的としたマッチング型イベントです。
企業だけでなく、農業法人、NPO、地域活動団体など、幅広いプレイヤー同士を結ぶケースが多いのが特徴です。
特徴
- 地域課題(人材不足・後継者不足など)と都市部人材のマッチングが中心
- オンライン・オフラインを組み合わせ、参加ハードルを下げた設計が主流
- 生活面の情報(住居支援、地域コミュニティ等)まで伝える工夫が重要
活用例
- 地方就職促進マッチング会(UIJターン支援)
- 地域×都市部NPOの共創プロジェクトマッチング
- 移住・創業希望者との事業引継ぎ型マッチングイベント
この地域創生・行政系マッチングイベントは、自治体や地域団体が主導し、地域活性化や移住・定住促進を目的とした交流の場です。特徴的なのは、単に企業だけでなく、農業法人、NPO、さらには地域活動団体といった幅広いプレーヤーが連携し、地域の課題解決を目指す点にあります。
特に、地域が抱える人材不足や後継者不足といった喫緊の課題に対し、都市部の人材やアイデアとのマッチングを重視しています。
参加へのハードルを下げるため、オンラインとオフラインを組み合わせた開催が主流となっており、より多くの人に参加の機会を提供しています。
地方への就職促進(UIJターン支援)から、地域と都市部のNPOによる共創プロジェクト、さらには移住・創業希望者と既存事業の円滑な引き継ぎまで、具体的な「活用例」が示すように、このイベントは地域の持続可能な発展に不可欠な出会いを創出しています。
単なる情報提供に留まらず、住居支援や地域コミュニティとの連携といった生活面の情報提供にも力を入れ、地域に根ざした新しい関係性を築くための重要な架け橋となるでしょう。
業界特化型・テーマ別イベントの事例紹介
特定の業界や課題に特化したマッチングイベントは、ターゲットの質と関心度が高いため、マッチング成功率も高い傾向があります。
特徴
- 参加者の関心領域が明確なため、高密度な商談・交流が可能
- テーマに合わせたトークセッションや共同ワークなどが設けられる
- 業界紙・専門メディアと連動したプロモーションが効果的
活用例
- 医療・介護分野の人材・技術連携マッチング会
- サステナビリティ・SDGs特化型の企業連携フォーラム
- ITスタートアップ向けVC・大手企業ピッチマッチング
目的に合ったイベント形式の選定が成果を左右する
マッチングイベントは、その形式次第で集まる層・生まれる成果・運営負荷が大きく変わります。
- 異業種交流で広く連携を促すか
- 採用・地域支援といった課題解決型か
- 業界に特化して深いマッチングを実現するか
目的とターゲットに応じたイベント設計が、マッチング率と参加者満足度を大きく左右します。
マッチングイベントのメリット・デメリット
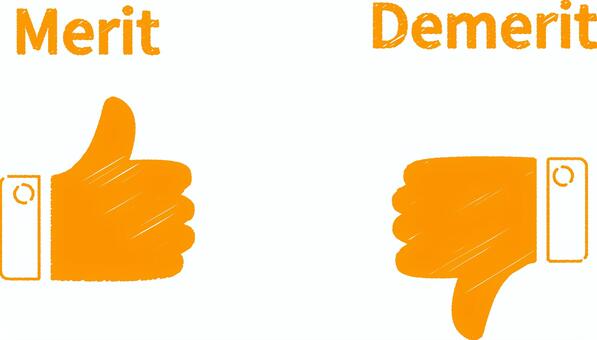
この章では、マッチングイベントの効果と注意点を以下の3つの視点から整理していきます。
- 参加者側にとっての価値
- 主催者・企業側にとっての活用メリット
- 起こりうる課題とその実践的な対策
マッチングイベントは、うまく設計・運営できれば高い成果と満足度を得られる手法ですが、準備不足や目的のブレがあると「ただ人が集まっただけ」で終わってしまうリスクもあります。
そのため、開催を検討するうえでは、主催者と参加者の双方にとってのメリット・デメリットを正しく把握し、対策を講じることが重要です。
参加者にとってのメリット
マッチングイベントは、参加者にとって効率的で有益な出会いの場として、多くのメリットを提供します。
主なメリット
- 効率よく複数の相手と出会える機会(短時間で多くの候補と接触可能)
- 普段出会えない相手・企業とつながるチャンス(業界外・他地域など)
- リアルな対話で「相性」や「社風」が見えやすい(求人票やLPだけでは分からない情報に触れられる)
- カジュアルな場によって、本音や個性が出しやすい(選考とは異なる空気感)
特に、採用・転職・起業志望者にとっては、「説明を受ける場」ではなく「自分の想いを伝えられる場」である点が大きな価値です。
主催者・企業にとってのメリット
主催者や出展側の企業にとっても、マッチングイベントは従来の展示会や説明会では得られない効果が期待できます。
主なメリット
- 見込み度の高いターゲット層と“直接対話”ができる
- 社風やビジョンをリアルに伝えられ、ブランディングにもつながる
- 求人・商談・連携などの“次のアクション”に直結しやすい
- 比較的低コスト・短期間で実施できる柔軟性がある
- 参加者の反応をリアルに収集できる場としてマーケティングにも活用可能
さらに、マッチング率や満足度を指標として蓄積すれば、自社の採用・営業活動の改善材料としても非常に有効です。
想定される課題とその対策(マッチング精度・時間配分など)
一方で、マッチングイベントには設計・運営における課題も多く存在します。
放置すると、参加者・出展者の満足度低下や“成果ゼロ”で終わってしまうリスクがあります。
よくある課題と対策
| 課題 | 主な原因 | 対策 |
| マッチングの“質”が低い | 参加者属性が合っていない/情報不足 | 事前にプロフィール・希望条件を収集し、マッチング管理ツールで組み合わせ精度を向上 |
| 時間が足りない・慌ただしい | 面談回数と時間設計が不十分 | 1対1形式・フリー交流・テーマ別トークの組み合わせ設計を行う |
| 話が深まらず終了してしまう | 初対面で話題に困る/進行が曖昧 | 進行ファシリテーターの配置や「事前質問リスト」の活用 |
| 終了後に連絡が途絶える | フォロー体制がない/手段が不明確 | 連絡先交換のフォーマット提供、事後アンケート・セカンドマッチの導線設計 |
重要なのは、イベントの“当日”だけでなく、
「前後を含めた設計とフォロー体制」を整えておくことです。
- 出会いの“質”と“量”を両立させるマッチング設計
- 参加者体験を高める進行と空間づくり
- 終了後を含めたフォロー体制の設計
マッチングイベントは、参加者・主催者双方にとって非常に高いポテンシャルを持つ手法ですが、設計の甘さが成果を大きく左右します。
これらを丁寧に構築すれば、「また参加したい」「次も出展したい」と言われるイベントへと成長します。
効果とリスクを理解し、設計と運用で成果を最大化しましょう。
オンラインマッチングイベントの可能性と活用方法

コロナ禍をきっかけに急拡大したオンラインイベントは、現在もなお「新しい常態」として定着しつつあります。
マッチングイベントにおいても、場所に縛られず参加できる利便性やコストパフォーマンスの高さから、オンライン開催を選ぶ主催者が増えています。
ただし、「対面での熱量が再現しにくい」「マッチング精度が落ちそう」といった不安の声も少なくありません。
そこで本章では、オンラインマッチングイベントを成功させるための考え方・ツール選定・設計ポイントを解説します。
オンライン開催のメリットと向いているケース
オンライン形式には、対面にはない強みが多数あります。
主催者の目的や参加者層によっては、オンラインのほうが適しているケースも少なくありません。
主なメリット
- 地理的制約を超えた集客が可能(全国・海外からも参加しやすい)
- 移動・会場コストの削減(参加者・主催者双方にとって経済的)
- 短時間・少人数でも柔軟に実施できる(1時間開催も可能)
- 録画・再視聴・資料配布などの拡張性
オンラインが向いている主なケース
- 特定業界や属性に特化した小規模マッチング会
- 初回接点や情報提供を目的とした“ライトな出会い”の場
- 地方企業×都市部学生など、距離を越えたマッチング
- 継続型イベントの中間チェックインや1on1フォロー
「深いつながり」よりも「出会いの機会創出」を主目的とする場合、オンラインはむしろ相性が良い形式です。
プラットフォーム・ツールの選定ポイント
オンライン開催において、使用するツール・プラットフォームの選定が“体験の質”に直結します。
ZoomやGoogle Meetのような汎用ツールで対応するケースもありますが、マッチングイベントならではの要件を満たせるかが重要です。
選定時にチェックすべき主な項目
| 項目 | チェックポイント |
| マッチング機能 | 1on1自動割当/プロフィール閲覧/推薦機能はあるか? |
| UI・操作性 | 非IT系参加者でも直感的に使えるか? |
| 同時接続数・安定性 | 想定人数に対応できるインフラか? |
| 参加者管理 | 出欠・予約管理・チャット履歴の取得が可能か? |
| アーカイブ対応 | 動画保存・資料ダウンロード機能はあるか? |
| 料金プラン | 月額制/従量制/カスタム対応の柔軟性 |
また、主催者のサポート体制がある国内サービスを選ぶと、トラブル時の安心感も高まります。
成功のための設計・進行・サポート体制
オンラインマッチングイベントでは、「リアル感」と「スムーズな導線」の両立がポイントです。
特に、参加者が慣れていないケースも想定し、進行とサポート体制を強化することで“離脱”を防ぐ工夫が必要です。
成功のための実務ポイント
- 開会前にルール説明+ツール操作のリハーサルを実施
- 「次に何をするか」が一目でわかるUI・ナビゲーションを用意
- 進行役・タイムキーパー・技術サポートを分担し、裏方体制を強化
- Zoomブレイクアウトや個別ルームの使い分けで“静的→動的”な流れを設計
- チャット・アンケート・感想投稿などを活用して双方向性を担保
また、当日以外にも「事前説明会」や「事後アンケート→再マッチ」などでイベント全体を分割設計することで、オンラインならではの柔軟さを活かせます。
オンライン活用は「設計力」と「ツール選定」がカギを握る
オンラインマッチングイベントは、適切な準備とツール選び、進行設計が整えば、対面を上回る成果を出すことも可能です。
- 地理・コスト・時間の制約を超えられる柔軟性とスピード感
- 目的に応じたイベント規模・形式の最適化がしやすい
- 操作サポート・導線設計・事前準備の工夫で“温度感のある交流”も十分実現可能
オンライン開催=味気ない、というのはひと昔前の話です。
これからは、リアルとオンラインのメリットをどう設計に取り入れるかが、主催者の腕の見せどころです。
次章では、マッチングイベントを成功に導くための企画設計と満足度向上のコツを具体的に解説していきます。
マッチングイベントを成功に導くポイント

マッチングイベントの成功とは、単に「多くの人が集まった」「予定通り終わった」という話ではありません。
参加者・出展者の双方が「来てよかった」と感じる出会いや成果を得られたかどうかが、本当の成功の基準です。
そのためには、企画の初期段階からゴールを見据えた設計が不可欠です。
この章では、成果につながるマッチングイベントに共通する3つの成功ポイントを紹介します。
目的設定とターゲット明確化の重要性
成功するマッチングイベントは、例外なく「目的」と「対象」が明確です。
“誰に何を届けたいのか”“どんな成果を期待しているのか”を最初に言語化できているかどうかが、すべての設計の起点になります。
主なチェックポイント
- 「課題解決型」か「交流・連携型」かを明確にする
- 参加者の属性・業界・職種・年齢層を具体化する
- 企業同士/企業と学生/企業と自治体など、マッチングの“軸”を整理する
目的とターゲットが曖昧なまま開催すると、「誰のためのイベントなのか」が参加者に伝わらず、結果的に満足度の低い“広く浅いイベント”になりやすくなります。
魅力的なプログラム構成と話題提供
参加者の満足度を高め、次のアクションにつなげるには、“出会いの質”をどう高めるかがカギです。
そのために効果的なのが、「場を温める話題」「交流が深まる構成」の設計です。
工夫できる構成要素
- 参加者の関心に応じたテーマ別ブース・トークセッション
- アイスブレイクに使えるクイズ・ワークショップ・共通点紹介
- “無言時間”をつくらないようタイムキーパーや司会者が進行をサポート
- 「質問カード」「プロフィールシート」など“会話の起点”を用意
さらに、企業や自治体による3分ピッチ・PRタイムなどを導入することで、短時間でも“伝えたいことが伝わる設計”が可能になります。
参加者・出展者の満足度を高める工夫
イベント終了後のアンケートで最も多い不満は、「思ったような人と出会えなかった」「時間が短すぎた」など、マッチングの質と体験価値に関するものです。
だからこそ、主催者はイベント体験の“心理的導線”にまで配慮した設計が求められます。
満足度向上の具体策
- 参加者の“見える化”(事前プロフィール掲示/入場時のカテゴリ表示など)
- 休憩エリアや話しかけやすい立ち位置の設計(導線・レイアウト)
- 事後に「また話したい人」と再接続できる仕組み(再マッチング申請・連絡フォーム)
- 写真・動画・資料をイベント後に共有し、記憶を定着させる
特に「行動しやすい仕掛け」があることで、イベント中だけでなく、その後の接点継続や成果獲得につながりやすくなります。
成功の鍵は「場づくり」より「出会いのデザイン」にある
マッチングイベントを成功に導くためには、華やかな演出や立派な会場ではなく、出会いの質をどう設計するかがすべてです。
- 目的と対象が明確なイベントは、集客も満足度も高い
- 対話が深まる話題提供・設計こそが“記憶に残る交流”を生む
- その後の関係性構築を見据えたフォロー設計までを一貫して行う
単なる「イベント運営」から一歩進んで、「出会いをデザインする設計者」としての視点を持つことが、主催者としての大きな価値になります。
次章では、主催者が必ず押さえておきたい実務チェックリストと運営の基本を整理してご紹介します。
主催・運営側が押さえるべき準備とチェックリスト

マッチングイベントの成功は、当日の進行だけでなく、事前の段取りがすべてを左右します。
特に法人・行政・団体が主催するイベントでは、参加者の信頼を損なわないようプロフェッショナルな運営体制と準備の徹底が必須です。
この章では、イベントを開催する上で絶対に押さえるべき3つの準備項目を整理し、実務担当者が使える具体的なチェックポイントをご紹介します。
集客・広報計画の立て方
どれほど中身が良くても、「適切な人が集まらないイベント」は成果に結びつきません。
集客はイベント運営の最初にして最重要のポイントです。
集客計画の立て方
- ターゲット(年齢・業種・属性)を明確化し、訴求内容を設計
- 募集開始時期は最低でも開催の1.5〜2ヶ月前が理想
- 告知手段を多角化
- 自社媒体(Webサイト、SNS、メルマガ)
- 他社媒体(プレスリリース、メディア掲載)
- 関係団体・学校・パートナーからの協力拡散
- 申し込み導線を簡潔にし、リマインドメールなどで歩留まりを防ぐ
また、告知用のバナー・チラシなどもイベントの「印象」を左右するブランディング要素となるため、丁寧に設計することが重要です。
会場・配信環境・備品の手配
リアル・オンライン問わず、会場環境と備品の手配は抜け漏れが許されない要素です。
万が一、当日にマイクが使えない・配信が途切れるといったトラブルが起きれば、それだけで評価が大きく下がります。
リアル開催でのチェックポイント
- 会場のアクセス/動線/レイアウトの確認
- 備品(机・椅子・マイク・プロジェクター・受付備品など)のリストアップ
- 電源・Wi-Fi・音響の動作確認
- 張り紙・案内表示・名札などの準備
オンライン開催での確認項目
- 使用プラットフォームの安定性・操作性チェック
- テスト配信の実施(登壇者・参加者それぞれ)
- カメラ・マイク・画面共有の動作確認
- 通信トラブル時のバックアップ体制(代替連絡手段など)
リアル・オンライン共通して「想定外に備える“1割の余裕”」を持った準備が理想です。
当日スタッフの役割と緊急対応マニュアル
イベント当日は、想定通りに進まないことも多いため、役割分担と緊急対応の備えがカギを握ります。
スタッフ配置の基本体制(例)
| 担当 | 主な役割 |
| 総合ディレクター | タイムキープ、全体進行の指揮 |
| 受付・誘導 | 出欠管理、案内、質問対応 |
| サポート係 | 機材トラブル・不明点の即対応 |
| 会場管理 | 動線確保、整理整頓、換気・消毒(リアル) |
| チャット・モデレーター | 質問整理、場の活性化(オンライン) |
緊急時に備えるべきマニュアル例
- 回線・マイク不良時の対応フロー
- 体調不良者の対応手順(リアル開催時)
- 想定以上の参加・欠席など人数変動への柔軟対応方法
- 主催者不在時に引き継げる「進行マニュアル」常備
“誰が何をするか”を事前に共有・シミュレーションしておくことが、当日の混乱を最小限に抑える鍵です。
イベントの成否は「準備の精度」で決まる
マッチングイベントの成功は、派手な企画よりも、地に足のついた準備と設計にかかっています。
- 明確な集客計画とターゲットごとの広報導線の構築
- 環境整備・備品確認による“トラブルゼロ”への備え
- スタッフ配置・対応マニュアルによるチーム運営の強化
これらを押さえておくことで、主催者自身の負担も軽減され、参加者に集中した良質な“出会いの場”の提供が可能になります。
単発で終わらせない!マッチングイベントを事業戦略に組み込む方法

マッチングイベントは、出会いや交流の場を提供するだけでなく、企業の営業・採用・広報といった複数部門に波及効果をもたらす“戦略的資産”になり得ます。
しかし、多くの企業や団体では、「とりあえず1回開催して終わる」ケースが少なくありません。
それでは費用対効果も蓄積されず、社内からの評価も得づらくなってしまいます。
本章では、マッチングイベントを単発で終わらせず、中長期の事業戦略にどう組み込み、活用していくかについて解説します。
営業・採用・PRとの連携による複合的な効果
マッチングイベントは、本来“複数の経営課題にまたがる可能性”を秘めています。
たとえば、以下のような部門横断型の効果を同時に狙うことが可能です。
【営業部門との連携】
- イベントを通じて見込み顧客との直接接点が持てる
- 商談や資料請求にスムーズに誘導できる仕組みを入れ込めば、リード獲得コストが大幅に下がる
- 顧客のニーズや反応をリアルに把握でき、商品・サービス改善のヒントにもなる
【採用部門との連携】
- 採用専用のマッチングイベントでなくても、職場の雰囲気や社員の姿勢を見せることがブランディングにつながる
- 営業や広報スタッフの現場対応が“働く人のリアルな魅力”として映る
- イベント後の学生フォローを人事部が担えば、採用活動との相乗効果も期待できる
【広報・ブランディングとの連携】
- 自社が主催することで、「つなぎ手」「仕掛け手」としての信頼感を醸成
- 地域・業界内での影響力強化、メディア露出の増加にもつながる
- SNSやWebサイトでの発信を組み合わせることで、認知から参加→取引→リファラルまでの流れがつくれる
このように、マッチングイベントは営業・採用・PRの“交差点”として設計可能です。
社内の複数部署と連携し、単発開催では得られない“部門横断的な成果設計”が成功のカギとなります。
年間スケジュールに組み込んだ継続型マッチング設計
「1回で終わるイベント」ではなく、年間で成果を積み上げていく“継続設計”にすることで、以下のようなメリットが生まれます。
【メリット1 – 蓄積されるデータとノウハウ】
- 参加者属性、マッチング成功率、参加後アクション率などの定量データが蓄積される
- イベントのタイミング別の効果を比較し、最適な開催時期や内容が見えてくる
- 失敗・成功の要因分析を通じて、回を重ねるごとにイベントの質が向上する
【メリット2 – 社内体制と予算計画が立てやすくなる】
- 年間スケジュールに組み込むことで、業務の平準化・予算確保がしやすくなる
- 社内関係者(営業・広報・採用など)のスケジュール調整も計画的に行える
- 定例化により、「●月はマッチング月」というような社内外の期待値形成にもつながる
【メリット3 – 外部パートナーや参加者との関係性が深まる】
- 毎年・毎期開催することで、「また出たい」「このイベントには注目している」というリピーターや紹介参加者が増える
- 地域や業界のパートナー(自治体・大学・協会など)と継続的な連携関係が構築できる
- 1回の成果では見えにくい「つながりの濃さ」が可視化される
たとえば、春=採用向け、夏=地域連携型、秋=新規事業マッチング、冬=フォローアップイベントなど、目的別に分けたサイクル設計も有効です。
主催イベントがブランド資産になる理由と実例
継続的にマッチングイベントを開催し、その成果を積み上げていくと、単なる催事が“企業ブランドそのもの”に変化します。
ブランド資産としての効果
- 「仕掛ける企業」「出会いを創る存在」という市場認知が得られる
- 自社の思想や価値観を、イベントという形で直接伝えられる
- イベントに参加した経験自体が「顧客との共体験」となり、他社との差別化要素となる
【実例1 – BtoB製造業の技術マッチング会(中小企業)】
地域の同業他社や大学研究室との交流を図るイベントを毎年実施。
開始3年目からは、「この会社のイベントには毎年参加している」という固定ファンがつき、技術提携→OEM受注にまで発展。
【実例2 – 地方自治体のUIターン就職フェア(行政)】
東京で年2回のマッチングイベントを継続開催。自治体の知名度は低かったが、参加企業と求職者の満足度が高く、口コミで拡散。
「信頼できる自治体の支援先」として、地方創生ブランドの一端を担う存在に成長。
【実例3 – IT系スタートアップによるピッチマッチング(民間)】
自社のサービス利用者と投資家・VCをつなぐピッチ型マッチング会を四半期ごとに実施。
スタートアップ支援の姿勢が評価され、採用や営業面でも「つながりがある企業」として好印象を持たれるようになった。
このように、イベントの価値は「場の提供」にとどまらず、「その企業が何を重視し、誰と未来を描きたいか」というブランディングにも直結しています。
マッチングイベントは“中長期的な資産”として設計すべき
マッチングイベントは、一度開催して終わる施策ではなく、事業や組織全体に波及する“戦略的資産”になり得る場です。
- 営業・採用・広報と連動すれば複合的な成果が得られる
- 年間スケジュールに落とし込むことでノウハウと信頼が蓄積される
- 継続開催により「仕掛ける企業」としてのブランドが醸成されていく
単発イベントから一歩進み、“続く設計・育てる設計”を意識することで、マッチングイベントは御社の中核戦略の1つとして機能し始めます。
社内を巻き込む!マッチングイベントを成功させる組織内の動かし方
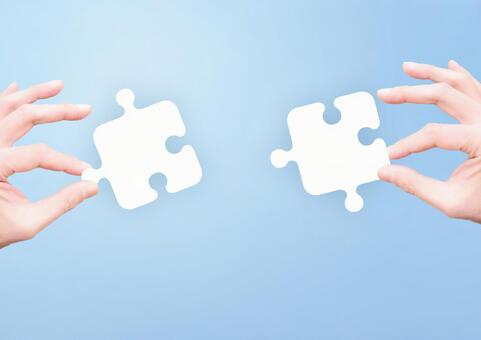
マッチングイベントの成否は、主催者の“企画力”だけでは決まりません。
特に法人主催の場合、営業・人事・広報など複数部署との連携なしに成果は生まれにくく、主担当者が孤軍奮闘してしまうケースも少なくありません。
だからこそ必要なのが、「社内を巻き込む力」。
イベントを“自分事”として捉えてもらい、部門横断でリソースと知恵を結集する体制づくりが、質の高いマッチングイベントを実現するカギになります。
この章では、社内巻き込みのための実践的アプローチを3つの視点で解説します。
営業・人事・広報との連携体制づくり
イベントを全社横断で推進するには、それぞれの部門が「自分たちにとってのメリット」を感じられる関係設計が必要です。
【各部門との連携メリット】
- 営業部門: リード獲得、関係構築の“導線”として活用可能
- 人事部門: 採用ブランディングや、企業文化の発信に貢献
- 広報部門: イベントを通じた露出機会や、ブランド強化につながる
【具体的な連携方法】
- 初期段階から関係各部署を「設計メンバー」として巻き込み、目的・ターゲット・期待効果を共有
- 定例会議で「イベントKPI(リード数、面談数、記事掲載数など)」を報告・連携
- 営業・人事・広報でそれぞれのミッションに合わせた役割設計を行う
重要なのは、「このイベントは、あの部署の仕事」ではなく、「自社全体の成果を最大化するための共通ミッション」だと認識してもらうことです。
社内協力を得るためのプレゼン・資料設計のコツ
社内巻き込みの第一歩は、企画段階で関係者を“納得・共感”させるプレゼン資料の設計です。
ただ単にイベントの概要を伝えるのではなく、“誰にどう役立ち、どんな成果につながるのか”を示すことがポイントです。
【資料に入れるべき要素】
- 開催目的と背景(なぜ今やるのか)
- ターゲットと期待する成果(例:新規リード●件、採用面談●件など)
- 各部門にとってのメリット・関与価値
- 役割分担案とタイムライン(参加をイメージしやすく)
- 過去の実績・他社事例など信頼につながる裏付け情報
また、短時間で伝えきる“3分版の口頭説明スクリプト”も併せて用意しておくと、上司や経営陣への報告にも使いやすくなります。
社内人材を活用したイベント力の最大化(登壇・広報・運営)
イベントに「外部講師」や「専門家」だけを呼ぶのではなく、自社の人材そのものを“資産化”することも非常に効果的です。
【活用できる社内リソース】
- 営業社員: 実際の業務内容や顧客対応のリアルな話が好評
- 若手社員: 就活生・求職者から“等身大で親近感がある”と高評価
- 技術者・開発者: 商品の裏側や仕事のこだわりを伝えるトークが強い差別化ポイントに
- 人事・広報: モデレーターや進行役、SNS発信の顔として活躍
【成功事例】
- 若手営業が登壇したパネルディスカッションが「一番印象に残った」というアンケート結果に
- エンジニアの開発裏話を紹介するミニセッションが予想以上に反響
- 広報担当によるSNSライブ配信で、イベント終了後もリーチが持続
このように、社内の“人”を前に出すことで、自社の魅力が“言葉”ではなく“体験”として伝わり、参加者の信頼と記憶に残るイベントになります。
巻き込んだ分だけ、イベントは育つ
マッチングイベントは、企画担当一人ががんばっても、「人・部署・視点」を巻き込まなければ本当の意味で成果は出ません。
- 部門ごとの目的を共有して「共通のゴール」に仕立てる
- 協力を得るための資料・説明の質を高め、社内説得力を強化する
- 社内人材を活用することで、“自社らしさ”が伝わるイベントに進化する
「自分がやる」から「みんなで創る」イベントへ。
その設計力こそが、マッチングイベントを単なる施策から“会社の成長エンジン”に変えるカギとなります。
マッチングイベント成功のカギは「設計力」と「継続力」

マッチングイベントは、単なる“交流の場”ではなく、明確な目的と設計によって成果を生み出す戦略的な手段です。
採用・営業・地域連携・オープンイノベーションなど、活用の幅は非常に広く、しかも短期間で信頼関係を構築できる効率的な仕組みです。
本記事では、企画段階から当日の運営、さらには事後フォロー・社内体制づくり・ブランド活用まで、成果を生み出すマッチングイベントの全体像を解説してきました。
押さえるべき要点は、以下の通りです。
- ターゲットと目的を明確にし、出会いの質を高める設計が必要
- 部門横断で連携し、イベントを事業戦略の一部として活用する発想が重要
- オンライン・オフラインの特徴を理解し、柔軟に選択することが成果の分かれ道
- 単発ではなく“継続的な接点”として位置づけ、PDCAを回して成長させていく
- 社内人材を巻き込むことで、企業文化や魅力がリアルに伝わるイベントとなる
企業や自治体が“つなぎ手”になることで、市場や地域の中で信頼される存在=選ばれ
る存在へと進化できます。
マッチングイベントの価値は「出会い」だけでなく、そこから何が生まれるか、どう
育てていくかにあります。
いまこそ、「集める」から「動かす」イベントづくりへ──。
貴社・貴団体に合ったマッチングイベントを設計し、次の成果につなげていきましょう。

コメント